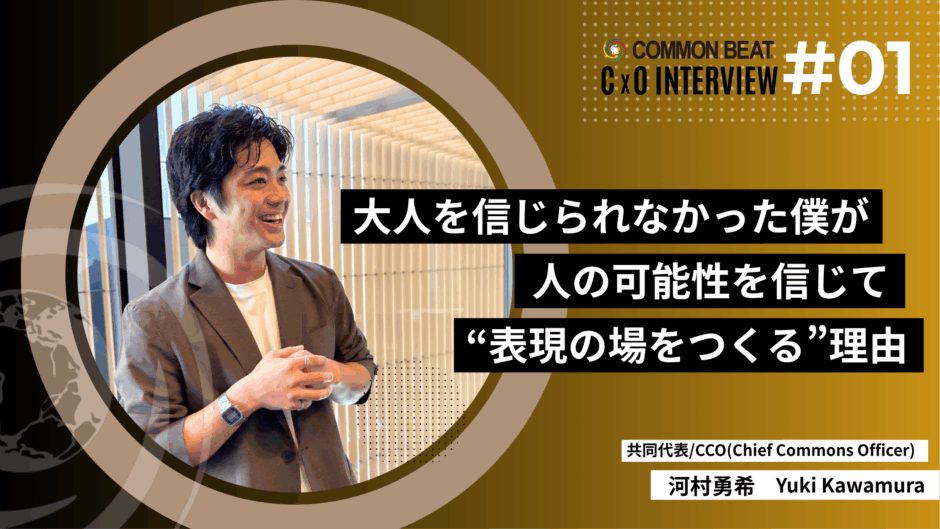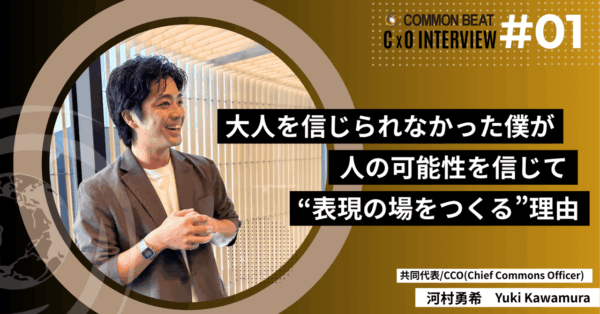2004年の創業から100人100日ミュージカル®プログラムを中心とした表現活動を通じて、人と人とのつながりを育んできたNPO法人コモンビート。2025年4月には、共同代表制とCxO制を導入し、代表理事 兼 CCO(Chief Commons Officer)に河村 勇希(ゆーき)が就任しました。彼が新たに立ち上げた「コモンズ事業」は、地域や教育の現場とつながりながら、共創の可能性を広げる挑戦でもあります。
これからの社会に求められる、“自己表現できる場”とは一体何でしょうか。そして、コモンビートが「個性が響きあう社会」を目指し、ミュージカルの枠を超えた表現活動にチャレンジするに至った理由とは。
「過酷な環境でドライになっていた自分がコモンビートに出会って変わったんです」と笑って話す18歳当時の原体験と、その背景にある想いについて話を伺いました。
▼記事全文はこちらをご覧ください。